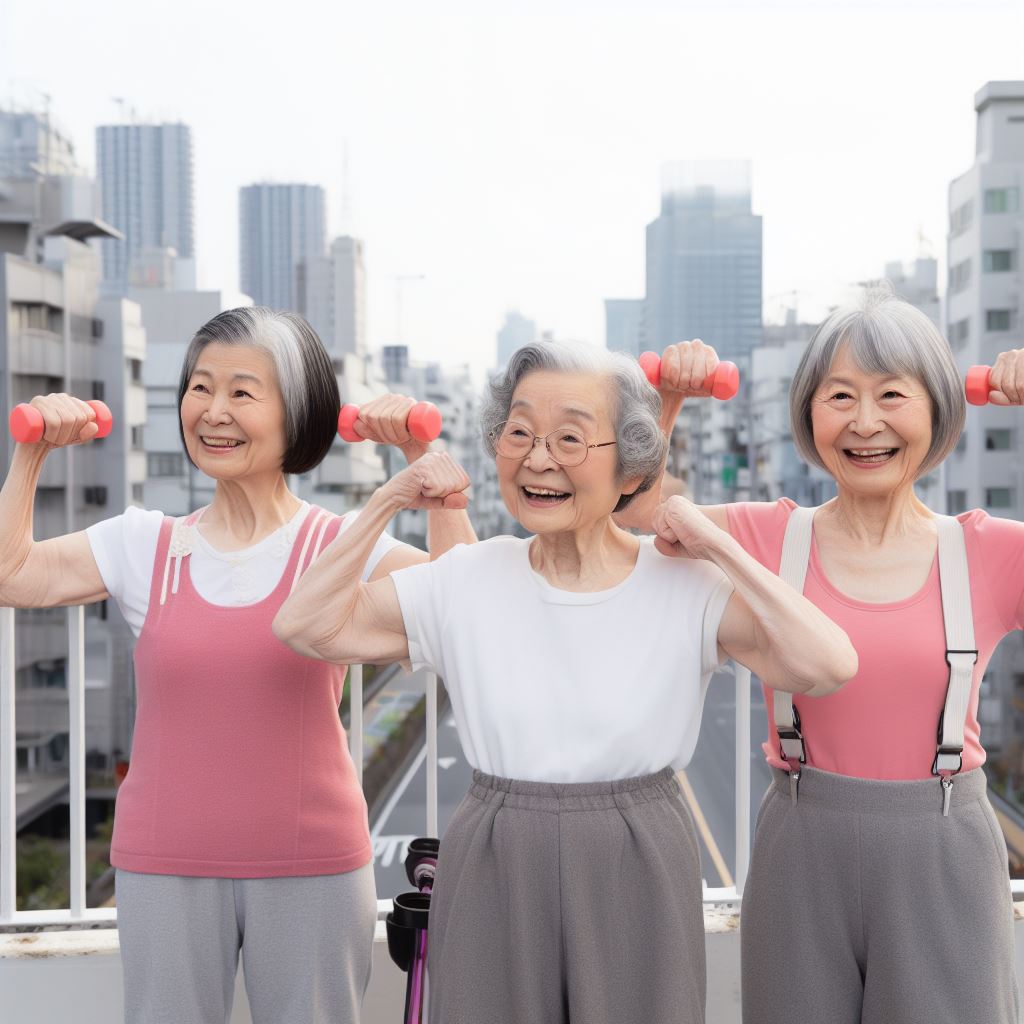町の端にひっそりと佇む小さな駅に、ふとしたことから通る人は少ない。駅舎は古びていて、ほとんどの窓にはホコリと蜘蛛の巣が張り巡らされている。駅のホームには座るベンチもないが、その向こうには一つのトンネルが闇に向かって伸びていた。
ある晩、陰りを増す夕暮れの中、村の年老いたおばあさんがその駅に向かって歩いていた。彼女の名前はミツコで、町の人々には親しみと尊敬の念を込めて“おばあさん”と呼ばれていた。ミツコは家を出て、夕食の買い物に向かう途中だった。
トンネルに近づくと、夕日の光はもうすっかり失われ、トンネルの入り口は暗黒の口のように見えた。しかし、おばあさんはその暗闇に恐れを感じることはなかった。彼女は何度もこの道を通り、夜のトンネルもただの通路と考えていた。
おばあさんはトンネルの入り口に立ち、前を見据えた。そして、急に不安を感じる。彼女は背中をそっと撫でた。そのジャケットの感触に助けられるように、彼女は勇気を振り絞ってトンネルに足を踏み入れた。
歩みを進めるおばあさんは、暗闇の中を進む影が見えた。その影が近づいてくると、おばあさんは手を突き出し、その人物に声をかけた。
「あら、もしかして、迷子になったのかしら?」
しかし、その影は無言で通り過ぎ、おばあさんの横を通り過ぎて行った。その人物の顔は見えなかったが、おばあさんは彼女が一瞬、老婆のように見えたことに気づいた。彼女は微笑んで言った。
「道を教えてあげればよかったわ。」
トンネルを進むおばあさんは、再び暗闇の中を見つめた。そして、もう一つの影が彼女に迫っているのを見つけた。おばあさんは今度こそ不安を感じ、声をかけた。
「お嬢さん、どこに行くの?」
影はおばあさんに向かって歩き続け、今度は声をかけてきた。
「おばあさん、助けてください。」
おばあさんはその声を聞いて、驚きの表情を浮かべた。声の主はもう一人のおばあさんだった。彼女は途方にくれているようで、老婆のような外見をしていた。おばあさんは声をかけられたおばあさんに近づき、手を差し伸べた。
「大丈夫、手を取って。」
おばあさんは手を取り、一緒に歩き始めた。彼女は年を取っているように見えたが、おばあさんは何か違和感を感じた。彼女の手は冷たかったし、歩く足元が浮いていた。
「あなた、幽霊?」
そのおばあさんはしばらく黙っていたが、ついに頷いた。
「はい、私は幽霊です。」
おばあさんは驚き、しかし怖れることはなかった。彼女は優しさに包まれた存在を感じた。おばあさんは尋ねた。
「どうしてここにいるの?」
幽霊のおばあさんは悲しげな表情を浮かべ、彼女の物語を語り始めた。それは彼女が若いころ、この町に住んでいたこと、そして幼い孫娘との幸せな思い出についての話だった。
しかし、ある日、彼女の孫娘は交通事故で亡くなってしまった。おばあさんは悲しみに暮れ、孫娘との思い出を求めて夜な夜なトンネルを訪れるようになった。彼女は孫娘と再び会うため、この世とあの世の境界をさ迷っていた。
「でも、あなたは幽霊になってしまったのね。」
おばあさんは幽霊のおばあさんに同情し、彼女の手を握ったままで話を聞いた。そして、彼女は言った。
「もう一度、一緒に歩きましょう。」
おばあさんは幽霊のおばあさんと共にトンネルを進み、彼女が思い出を求めてさまようことはなくなった。